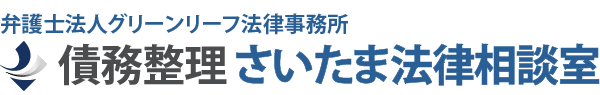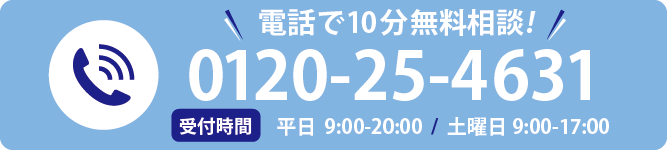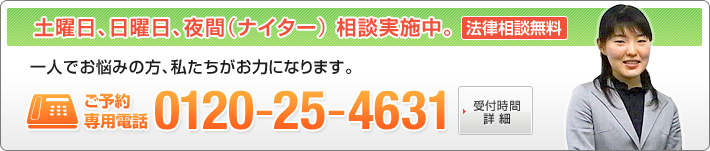紛争の内容
本債務者は、本申立1年程前に、従来就業していた会社に転職し、そのメインの仕事以外に二つのアルバイトを掛け持ちしている給与所得者です。
配偶者もメインの仕事共に、アルバイトを掛け持ちしています。
両名の収入を合算すると十分な収入がありますが、住宅ローン債務以外の、一般再生債権のうち、過半数を超える保証会社的立場の債権者があり、同債権者が小規模個人再生事件を申し立てた場合における、最低弁済額をクリアする再生計画案に同意しない場合を懸念して、給与所得者等個人再生手続を申立てました。
ただ、転職後、安定収入を得て1年ほどしか経過していなかったこと、また、申立直前に労災事故に遭い、アルバイト収入がなくなり、申立人の収入が大幅に減額したこともあり、収入の安定性を吟味するために、個人再生委員が選任されたものです。
本債務者の給与所得の継続性・安定性も一応問題となりましたので、その点も検討をすることが求められました。
交渉・調停・訴訟などの経過
まず、個人再生委員に選任されると、本再生手続きを解するのが相当か否かの意見を述べることになります。
(1)収入の状況(将来の収入見込み)について
本申立人債務者は、収入状況(その後の収入見込み)については、労災被害後の復職後の収入回復を見ます。また、メインの仕事の合間に、アルバイトを掛け持ちしているのですが、その勤務ぶりを見ると、身体を壊さないか心配するほどの仕事ぶりでした。
債務者に確認すると、もうかれこれ、20年以上、そのような時間で働いているので、負担とは感じておらず、また、申立時は二つのアルバイトをかけもちしていましたが、それを収入の良い一つのアルバイトに絞るとのことでした。
配偶者の方も、メインの仕事を充実させ、副業のアルバイトとのバランスをとるとのことで、配偶者の収入の安定性も確認できました。
履行テストでは、二口の住宅ローン以外の債務総額は、開始決定日の前日までの遅延損害金を入れると、1500万円を超える再生債権額となりますから、最低弁済額は金300万円となり、これを3年の分割で支払いたいとの希望でしたので、月額の負担を8万4000円とし、その金額で、再生委員口座に毎月送金してもらう、履行テストを行うこととしました。
給与所得者等再生手続の、収入の安定性は、過去2年間の就業状態、収入を見ますが、転職先に継続勤務され、アルバイトも継続するとのことから、安定性も見込めると判断しました。
よって、裁判所には、開始相当の意見を出しました。
裁判所は、本手続きの開始決定をなし、手続が始まりました。
(2)再生計画案の記載方法の問合せ(住宅ローン特則)
本債務者は、住宅ローン付きの住宅を保有し、当然ながら、住宅ローンを支払いつつ住宅の維持を強く希望しています。そのための、本申立です。
手続進行中、代理人から、再生委員に、次のような問合せがありました。
① 債務者所有建物(不動産)の第一順位抵当権者は、住宅ローン債権の譲受人である、債権者Aに、(抵当権者)名義(変更)がなされている。
② 他方、債務者所有建物(不動産)の第二順位抵当権者(C銀行)は、住宅ローン債権の譲受人である債権者Bに、(抵当権者)名義の変更がなされていない。
③ 第二順位抵当権者は(抵当権の)第三者対抗力を有していないのであれば、清算価値基準算定のために、同再生債権者(債権者B)は、抵当権の優先弁済効力を発揮しえず、同住宅ローン債権残額を控除できない。
④ なお、同住宅ローン債務の滞納、破産による支払い停止などの場合には、原債権者のC銀行が、債権者Bから同住宅ローン債権を買い戻し、抵当権者(名義人)と住宅ローン債権者が同一になるとの説明を受けた。
⑤ 清算価値保障原則の趣旨から、破産の場合には、結果的に原住宅ローン債権者C銀行が優先弁済を受けることになる以上、個人再生においても、現債権者(債権者B)が有している債権についても、不動産の価値から控除されるべきである。
⑥ 上記のような考えに基づいた場合の、再生計画案の記載については、どのようにしたらよいか。
(3)個人再生委員の意見(本件の検討)
次のように考え、裁判所に意見を求めました。
①抵当権の随伴性による、譲受債権者への移転
ところで、原債権者であるC銀行の住宅ローン債権を(第三者対抗力ある、確定日付ある通知ないし承諾により)、債権者Bに債権譲渡したものであれば、同住宅ローン債権の債権譲渡は第三者対抗力を有します。
そして、同住宅ローン債権を被担保債権として設定された抵当権は、その随伴性により、C銀行から譲受債権者である債権者Bに移転します。
② 民事再生法198条1項
同条項は、再生債務者が住宅資金特別条項を定めることができる場合について規定します。
住宅資金特別条項は、別除権を有する者の権利などに変更を加えるものであり、また担保割れしている部分についても、一般再生債権者と別の規律をするものであるので、厳格に特定する必要があるとされます。
③弁済による代位の例外
法198条1項但書は、民法500条の規定による弁済代位の場合には、住宅資金特別条項は定めることはできないとされます。他方、弁済者代位ではなく、住宅資金貸付債権を債権譲渡取得したものなどは含まれないとされます(注釈民事再生法1039頁)。
④住宅資金貸付債権を被担保債権とする抵当権の設定
住宅に、同債権を担保するための抵当権が設定されていることが必要です。本特則の目的は、再生債務者の住居の保持にあります。仮に抵当権が設定されていない場合には、一般債権の実行は手続開始により当然に禁止されます(法39条1項)ので、あえて特則を設ける必要はありません。
他方、再生手続上、抵当権は、別除権として自由な実行が保障されている(法53条)ので、仮に特則がなければ、その別除権の行使により、住宅は競売に付され、売却されてしまいます。そこで、特則適用の前提として、抵当権設定が要件とされたものです。
⑤ 上記抵当権は別除権たること
この別除権行使の危険を法的に回避するためとすれば、その抵当権は、別除権として認められるもの、つまり、他の再生債権者に対抗しうるものでなければなりません。民事再生法における別除権(53条1項)として認められるためには、その基礎となる担保権が、他の再生債権者に対抗しうるものでなければならないとされます。再生債務者等は、対抗要件の欠缺を主張できる第三者に該当するとされます。再生手続開始後は、再生手続開始前の原因による登記・登録は、再生手続の関係では、原則として、その効力を主張することができません(法45条)。したがって、再生手続開始決定時に対抗要件を備えていなかった担保権は、原則として、その後も対抗要件を備えることはできず、再生手続においては、別除権としての効力は否定されるとされます。
⑥ 清算価値保障原則
再生債権者の一般の利益との抵触する(法174条2項4号)とは、特定の再生債権者の一般の利益ではなく、再生債権者全体としての利益が、実質的に害されることを意味すると解されています。その典型的な例は、再生計画による弁済が破産手続による配当を下回る場合です。
本申立代理人は、本債務者の債務整理方針が、自己破産申立になる場合、上記原債権者の住宅資金貸付債権の買戻しがなされ、破産法上の別除権として処遇される(されてきた)から、それに比すれば、他の再生債権者の清算価値保障原則は全うされるとの趣旨であると理解されました。
「再生債権者としての利益が、実質的に害されること」は、つまり、清算価値保障原則を満たしているかどうかの判断は、再生計画に基づく弁済額と、破産手続による場合の予想配当額のほか、手続による時間の長短、費用の多寡、財産の換価の難易、履行の確実性などを総合的に考慮して行うべきとされます。
(4)本件検討
債務者(申立人)の希望はもっともですので、それを実現できる方策がないか、他の規定への抵触を可及的回避する方策を考えました。
① 清算価値保障原則の維持
本再生債務者は、本件住宅ローン特則付個人再生手続の再生計画案による弁済を行える見込みがない場合、つまり、住宅を手放さざるを得ない場合には自己破産必至となります。
自己破産必至である場合には、第一順位抵当権者は別除権者として、相応の優先弁済を受け、まだ、第二順位抵当権者として、住宅ローン貸付債権の原債権者が破産法上も別除権として処遇されるならば、やはり相応の優先弁済を受ける。
本物件はオーバーローンであるから、他の再生債権者(破産手続においては破産債権者)は少額の配当か、異時廃止を受け入れざるを得ないであろう。
すると、この見地からは、現債権者(債権者B)を住宅ローン特則の適用のある債権者として、処遇することが望ましいことになる。
② 「住宅貸付債権を担保する建物への抵当権」の解釈
住宅ローン特則付き個人再生は、再生債務者に住宅ローン付き住宅の保持を認め、他の再生債権者に、上記①の基準をクリアした弁済を義務付けるものである。
法196条3号の「抵当権」を、本手続き利用の、住宅ローン貸付債権を被担保債権であることのみを意味し、再生債務者、その他の再生債権者に対抗できる別除権であることを要しないと考えることができないかと考えてみます。
再生債務者は第二順位抵当権は、譲受債権者である債権者Bであることを否定はしませんし、その他の再生債権者としても、住宅は、住宅資金貸付債権の担保に取られており、オーバーローンであれば、当該不動産からの配当は受けられないことはやむを得ないと認識しているはずである(つまり、破産した際の清算価値保障は、少額配当か異時廃止による無配当を甘受せざるを得ない)からです。
③ 本件再生手続を廃止として、再度の申立てを検討する(消極)。
形式的には、第二順位抵当権を民事再生法53条に基づく別除権として認めることができないことから、法198条の住宅資金特別条項を定めることはできますが、第二順位抵当権の負担がないものとして、住宅の価値を考えなければなりません。
すると、その場合による、再生計画案の確実な履行は再生債務者は行いえないと考えられます。
そこで、本手続を廃止し、第二順位抵当権の住宅資金貸付債権の債権譲渡当事者の理解協力を取り付け、譲受人債権者の抵当権者名義の登記を済ませて、改めて、住宅ローン特則付き個人再生手続を申立てることが考えられます。しかし、これも、原債権の譲渡に遅れた抵当権登記の具備として、対抗要件否認の対象となり、個人再生手続においては、同額分の再生計画に基づく弁済額の増加が不可避となります。
なお、本件申立後、本件事象を再生手続裁判所、個人再生委員が認知し、その抵当権名義の不備を指摘し、それを具備した場合であっても、やはり、対抗要件否認の問題は不可避と考えられます。
④ まとめ
個人再生委員として、民事再生法の誠実に適用した再生計画案の立案を指導するとすれば、第二順位抵当権は法53条の別除権の要件を具備していない以上、清算価値保障基準を全うしようとすれば、本件不動産の価値から控除できるのは、第一順位抵当権の被担保債権額のみとなると考えられますが、これでは、おそらく、到底返済しえないであろうと見込みます。
他方、第二順位抵当権は、他の再生債務者への対抗力はないが、他の再生債務者も、本再生債務者が自己破産を選択し、最悪異時廃止とならざるを得ないことを甘受しなければ、その別除権の無効を主張しないのが経済的合理性ある態度・対応と推定されます。
すると、本件手続きを維持して、個人再生手続における清算価値保障原則の全うと、再生債務所の住居の確保を両立する希望を実現することが望ましく、その必要を全うするにはどうすべきかと、やはり、裁判所に意見を求めました。
(5)裁判所の見解
再生委員の見解はもっともであると思料されるが、再生債権者から再生計画に意見が出たら、改めて検討することとして、再生計画案の記載方法が案内されるとともに、債権譲渡日の特定などの追加情報の提供を促すよう指示を受けました。
【住宅資金特別条項の定め】は次のようなものです。
1 住宅資金貸付債権を有する債権者の氏名又は名称
2 対象となる住宅資金貸付債権
3 住宅及び住宅の敷地の表示
別紙物件目録記載のとおり ←と記載します。よって、不動産登記記録全部事項証明書(不動産登記簿謄本)から、正確に引き写す。
4 抵当権の表示
別紙抵当権目録記載のとおり ←と記載します。よって、不動産登記記録全部事項証明書(不動産登記簿謄本)から、正確に引き写す。
※ しかし、抵当権者≠譲受債権者であることから、形式的な引き写しでは不正確となります。
そこで、何らかの作業が必要となります。
これにより、裁判所からアドバイスを受けたのが、登記簿の記載から、原抵当権の設定内容を引き写し、但書で、原住宅ローン債権の譲渡日、譲受人を記載し、その移転登記が未了であることを明示する方法でした。
(6)再生計画案に対する意見
本債務者は、収入の安定性、継続性も認められ、また、履行テストも万全にクリアしておりましたので、再生債権者の意見を問うなど手続きをするのが相当とする意見書を提出しました。
本事例の結末
本再生計画案に、意見を述べる再生債権者はありませんでした。
よって、裁判所は本計画案を認可しました。
本事例に学ぶこと
本申立により、住宅ローン特則の、住宅ローン債権の別除権たることについて、再検討する機会となりました。
このような住宅ローン債権、その抵当権移転の問題については、住宅ローン商品によっては想定しておかねばならない問題と認識を改めました。
住宅ローン会社は、住宅ローンを組んだ債務者が、将来、住宅ローン付き個人再生手続を利用することを想定してはいないでしょう。
よって、住宅ローン原債権を債権譲渡しながら、譲受債権者が抵当権設定登記の名義変更をすることが確実となるかは期待できないと考えます。
このようなことに問題意識を共有している当事務所では、個人再生手続の十分な申立経験もありますので、ご遠慮なく、まずは電話相談、そしてご来所での相談を受けられ、ご依頼され、住宅の維持を図りつつ、経済的更生の道を歩んでいただければと思います。
当事務所は、このような債務整理を得意としておりますので、きっとお力になれるはずです。
弁護士 榎本 誉