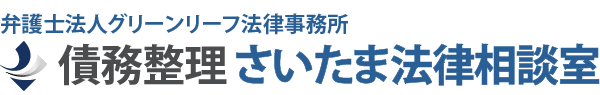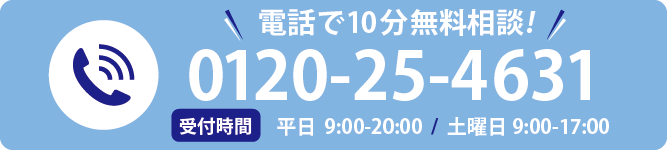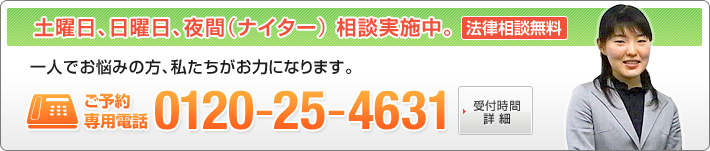ご依頼の状況(破産管財人とは)
当事務所の弁護士は、さいたま地方裁判所より、個人の自己破産申立案件における「破産管財人」に選任されました。
破産者は、過去に個人事業主として事業を営んでおり、破産手続が開始された時点でも、事業で使用していた機械や在庫などの「動産」が残されていました。
しかし、その保管場所では、破産者の所有物と、取引先など第三者の所有物とが混在してしまっている状況でした。そのため、管財人には、これらの財産関係を法的に整理し、適切に処分することが求められました。
破産管財人としての主な業務内容
裁判所から選任された破産管財人として、以下の業務を遂行しました。
・財産の調査・分別
本件の最大の課題は、他人の物と混在している動産の所有権を特定することでした。破産管財人は現地に赴き、破産者本人や関係者からの聞き取り、契約書や管理台帳などの資料を精査し、どれが破産者の財産(破産財団)に属し、どれが第三者の所有物かを法的に分別・特定する作業を行いました。
・動産の換価(売却)と費用回収
破産者の財産であると特定された動産について、破産管財人は裁判所の許可を得て、売却処分(換価)を進めました。その売却代金は、破産手続の費用(管財人報酬を含む)や、債権者への配当の原資として、破産財団に組み入れられました。
・債権者集会への報告と免責調査
破産者の財産調査、換価業務の経過、および借入れの経緯(免責調査)について、裁判所及び債権者が集まる「債権者集会」で報告しました。
本事例の結末(結果)
動産の売却により一定の費用は回収できたものの、全債権者に対して配当(返済)を行うほどの金額には至りませんでした。
そのため、破産管財人は、確保した財産から破産手続費用を支払うことをもって破産手続を終了する「異時廃止」が相当であるとの意見を裁判所に報告しました。債権者集会は1回で終了し、手続は迅速に終結。その後、破産者については免責(借金の支払い義務の免除)が許可され、経済的な再スタートを切ることができました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
個人事業主の方が破産する場合、個人の財産と事業用の財産、さらには本件のように第三者の財産が複雑に絡み合い、財産関係が不明瞭になっていることが少なくありません。
破産管財人は、そのような複雑な状況であっても、法律の専門家としての中立的な立場で、一つひとつの財産を冷静に調査・分別し、法に則って適正に処理・換価する役割を担います。
もしご自身の破産手続で管財人が選任されたとしても、それは財産関係を公正に整理し、誠実な再出発をサポートするために必要なプロセスです。財産状況が複雑であることを理由に破産をためらう必要はありませんので、まずは専門家にご相談ください。
弁護士 時田 剛志