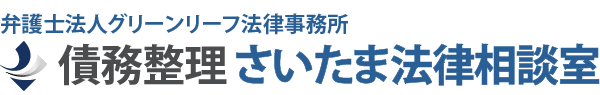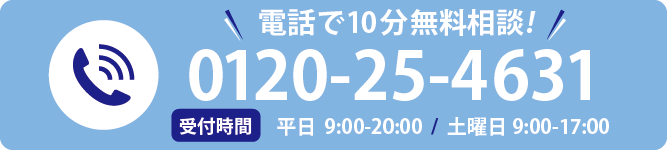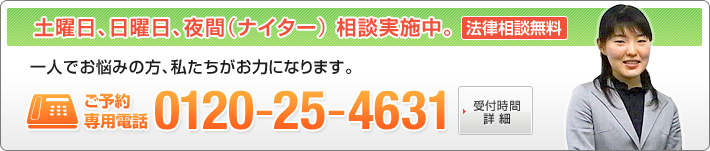紛争の内容
1 マンションなどの不動産投資による多額の負債、給与の差押え
破産者は医療従事者として稼働していました。
マンション投資も行い、最盛期には各地にマンション(区分所有権)を持ち、また、地方には共同住宅1棟全部を保有し、不動産賃貸業も行っていました。
不採算などから、保有する投資物件を任意売却して、債務を整理していましたが、数千万円の負債を抱えていました。
弁護士に債務整理を依頼し、同弁護士が各債権者に受任通知を発し、申立準備に入りましたが、その間に、投資用資金のローン会社の保証会社から訴訟を提起され、結果、勤務先の給与の差押えを受けてしまいました。
2 破産手続開始決定を受け、給与差押の債権執行、差押債権者からの回収
申立代理人の受任通知発送、債権者受領後の給与差押でしたので、当該債権者が第三債務者である、破産者の勤務先から回収した全額が否認権の対象となります。
そこで、まず、破産手続開始決定を受けたことから、破産者の給与に対する債権執行を取り消されたいとして、強制執行の裁判所に、その旨の上申書を提出しました。
次いで、否認権対象行為である、債権者の債権執行による債権回収した全額を破産管財人の口座に振り込んで支払うよう通知書を発送しました。
同通知を受けた債権者から、同債権執行までの、破産者との交渉経緯などの説明を受けましたが、法的に考慮すべき事情はなかったため、満額の返済を求める方針に変わりなく、支払いを求めました。
債権者の担当者は、否認権行使を受けることは想定していたとのことで、満額の送金がなされました。
3 マンションの任意売却
債務者の自宅であるマンションについては、競売手続が先行していました。
そこで、競売申立債権者に、破産管財人として、任意売却をしたいと申し入れ、了解・協力を取り付けました。複数不動産業者の査定を取り付けましたが、ほとんど査定額は変わりませんでしたので、同じ市内の不動産会社と媒介契約を交わし、破産者のマンションを任意売却する手はずに着手しました。
仲介の不動産会社が、居住している破産者の協力を取り付け、マンション内部の点検をしました。
担当者が室内点検をしたところ、本件マンション内部には、天井(おそらく、ルーフバルコニー)からの雨水の侵入があること、キッチンスペースの冷蔵庫の床が腐食していること、新築後30年以上経過していることから室内設備の劣化も相当程度進行していることなどから、現状有姿売買の方針では積極的な販売活動が困難として、不動産会社から、本件売買の仲介依頼を取りやめとしたいとの申し出がありました。
その際、内部の写真の提供も受けました。
確かに、同マンションの内部はかなり荒れた状態でした。
そこで、任意売却による早期売却、売却金の一部の財団組入れ実現は難しいとして、裁判所に、本件マンションの放棄許可申請を行い、財団からの放棄が許可されました。
4 破産者の死去
破産者は糖尿病を患い、自宅透析を続けながら、医療に従事していました。
開始決定後の管財人との面接には足の指の切断処置を受けていることから、義足をつけ、杖を突いての来所でした。
申立代理人より、破産者の糖尿病の症状が悪化し、結果、下肢を大きく切断することになったこと、次回の集会には出頭できないことなどの報告がありました。
その後、代理人から、下肢切断後、義足の調整も済み、次回集会には出頭するとの連絡を受けてから、間もなく、破産者がお亡くなりになったとの報告を受けました。
5 破産者の死亡、破産手続の続行
破産手続は、亡くなった破産者の相続財産の破産手続として続行されました。
そして、破産手続中に死亡した破産者の免責手続はありません。
数千万円以上の負債を抱えた破産者でしたので、相続人となった配偶者、そして、第一順位の相続人であるお子さんらは、同負債の相続から免れるためには、家庭裁判所で相続放棄申述受理の手続をとる必要があります。
申立代理人は、破産者の相続人らの手続に関与したようでした。
競売手続は続行されており、同申立債権者が相続人調査をしています。
破産者の第三順位の相続人である兄弟姉妹まで調査し、その方々が相続放棄をしたことを確認する必要があったようです。
また、本件マンションは状態として好ましくないため、なかなか買い手も現れなかったようです。
6 少額配当
不動産競売事件は破産事件とは別個の手続です。
よって、競売手続において配当要求している債権者は破産債権者でもありましたが、破産手続において破産債権届出をしている債権者に、管財人が換価し、また、回収した財産から配当を行うことになりました。
破産債権者とマンションの競売手続の債権者である別除権者においては、その競売手続で配当を受けられない額を証明してもらい、配当額を確定します。
その届出をしない別除権者には、その届出債権額全額を認めないこととしました。
他方、第一順位抵当権者、第二順位抵当権者への配当は見込まれるが、第三順位抵当権者である破産債権者はその見込みがないとしての報告があり、同債権者については全額を認めました。
また、マンションの滞納管理費、修繕積立金については、破産決定前の未払い分、破産決定後の未払い分を峻別しました。
マンション滞納管理費・修繕積立金については、法律書籍では、特別の先取特権があり、それは破産法上別除権付債権となり、不足額の証明が必要な別除権債権であるとする解説が多いようです。
他方、当事件の破産裁判所は、その見解に与しませんでした。
手続進行のために、裁判所の指示に従い、対応しました。
ところで、破産者は、マンションの居室以外に、マンションの管理組合から、ベランダを賃借しており、賃料債務がありました。これについては、任意売却対応をしていたためもあり、財団債権として支払対応しました。
また、配当表の更正なども行ったことなどを経て、各債権者に配当を完了し、その終了を集会で報告し、管財事件は終結しました。
本事例の結末
債権者には、簡易配当を行いました。
破産手続中の破産者が死亡したため、免責手続は行われません。
本事例に学ぶこと
債務者・相談者が多額の借入金で不動産投資をしている場合があります。
不採算の物件を任意売却し、優良不動産で経営の立て直しをする場合がありますが、それが上手くいくとは限りません。
結果、破産申立を検討します。
今回の事例では、債務名義を有する債権者に、給与差押を受けて、相当額を回収されてしまった後の申立て、破産手続開始決定でした。
破産管財人の業務は、債権執行裁判所に、破産手続が開始されたことから、その債権執行手続の取消の上申書を提出することから始まります。
次いで、支払停止を意味する受任通知後の債権回収額の返還を求め、否認権を行使します。
今回の事案では、債権執行債権者は、管財人からの否認権に基づく返還請求は想定していたとのことでしたので、スムーズに満額の回収がかないました。
これが多額であったため、マンションの任意売却による財団組入金に期待せずとも、各債権者に少額ですが配当がかないました。
また、今回の事案では、闘病中の破産者が手続中に死亡するという想定外の進行を見ました。
債務者におかれては、弁護士に依頼後、弁護士費用の分割払いなどの事情で、受任後まもなくの破産申立ができない場合があります。
そのような場合には、債務名義を得た債権者からの給与差押のリスクもあります。
当事務所では、受任の際に、そのようなリスクもご説明申し上げています。
破産手続のメリット、デメリット、申立までに時間を要する場合のリスクなどもご説明し、受任に至ります。ご質問にも丁寧に回答することを心がけておりますので、当事務所に債務整理をご相談、ご依頼ください。
弁護士 榎本 誉