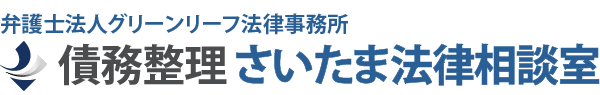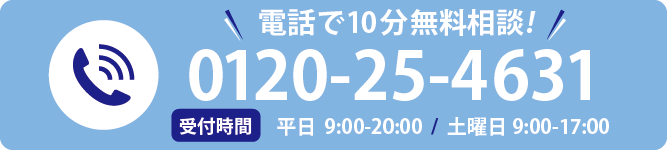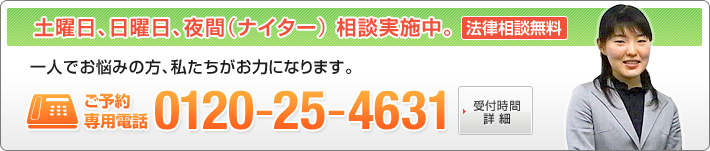紛争の内容
債務者は法テラスの相談担当弁護士に自己破産手続の申立てを依頼したが、その申立内容に多数の不備があり、裁判所の追完指示に従った報告がなされないなどの不備があり、破産管財人として、破産申立の事情などを補充調査を指示された破産管財事件です。
交渉・調停・訴訟などの経過
破産者の体調不良などがあって、管財人との面談日がたびたび順延され、第1回債権者集会の10日前にようやく、管財人面談がかないました。
管財人から、改めて破産者に、本申立に至った事情を聞き取りました。
1 初めての借入(ローン購入)
平成8年11月ころ、破産者が千葉県で保険外交員をしていたころ、夫の友人から、補正下着の照会販売に誘われたそうです。当時の職業から顧客の方へのセールスも見込まれたようですが、結局、破産者自身の下着を色違いで2セット購入し、その際のローンを組んだのが初めてのローンでした。
月額1万円位でしたので、当時共働きであり、破産者個人としても月額手取り18万円から19万円を得ていましたから、特に負担には感じなかったようです。
この債権は完済できず、平成12年債権譲渡され、平成19年から20年ころまで分割金を支払っていたことが認めらました。
この当時の引き落とし口座が県内の地方銀行でしたので、その口座の有無も管財人から調査しましたが、存在しないとの回答でした。
2 消費者金融数社からの借り入れ、過払い金返還請求権の時効消滅
共働きであった夫が、給与をギャンブルにつぎ込むのようになり、家計負担を破産者のみが行わざるを得なくなったようです。
破産者は、3つの仕事を掛け持ちし、働きましたが、消費者金融3社から生活費の不足を補うため借入をしたそうですが、すべた完済したとのことでした。
当時の借入と返済は、利息制限法の法定利息を超えるもので、過払い金が発生していたと想定されましたが、完済から優に10年以上経過しており、消費者金融からは、過払い金返還について消滅時効を主張されるのは明らかですので、回収はかないませんでした。
3 長女の進学費用の借入
破産者は、長女の進学のために、国民生活金融公庫から、借り入れを行い、学費に充てていました。
しかし、その後、破産者は体調を崩し、仕事に就けなくなったとのことです。
子の学資の返済は、連帯保証人である元夫が支払い、その後、長女が支払い続けていました。
そこで、元夫の方、長女の方を債権者として追加しました。
4 生活保護を受けるまでの間の生活維持の方法
破産者は、平成24年ころ以降は鬱により体調がすぐれず、仕事についていませんでした。
その間の、生活をどのように賄っていたかというと、二人の子供に支給される、扶養児童手当(月額56,250円)、児童手当金2万円(4カ月ごと8万円)で生活をし、また、成人した長女が生活費を負担するなどして、何とか生活していたとのことでした。
5 メルカリ・メルペイの利用
破産者は、メルカリを利用して、子供衣服や、食材などを購入していたといいます。
その支払については、破産者がクレジットカードを保有していないことから、どのように支払っていたかを問うと、コンビニ払いを利用していたといいます。
その後、メルカリ運営会社が後払いシステムを設けたことから、破産者は、後払いシステムを利用することになりました。このシステムは、これまでの(フリマアプリの)メルカリ取引に応じた、「メルカリ月イチ払」からさらに、「メルペイ後払い」というシステムになり、後払い利用が可能になったもので、2019年ころから利用していたといいます。
ところで、破産者は、平成31年(令和元年)、生活保護受給を開始しました。
メルカリ後払いシステムを利用に際し、生活保護受給者を申告する機会はなく、メルカリのシステムの設定に応じたのみであるので、破産者には、メルカリに対する積極的な詐術は認められませんでした。
6 債権回収会社からの取立てに苦慮し、法テラスに相談
本破産者は、生活保護受給申請の際に、保護費は借金の返済に充ててはいけないと説明を受けていました。
その後、債権回収会社からの取立ての通知が頻繁に来るようになりました。
破産者は、生活保護費を取立ての会社に支払ってはいけないと指導を受けていましたので、どうしたらよいのか分からず、悩んでいたところ、インターネットで「法テラス」を知り、法律相談を受けたそうです。
その際の担当弁護士が、申立代理人弁護士であり、同弁護士を通じて、法テラスの法律扶助を申し込み、正式依頼し、今般に至ったとのことでした。
当然ながら、申立代理人弁護士に依頼後は、債権者に支払ったことはありません。
7 現在の生活
破産者の家計の状況に、電話代2万円とあり、収入に応じて過大ではないかと気になりました。
事情を確認すると、元夫が元夫との間の子らのことが心配であるのでとして、隣の市に住む元夫が携帯電話代を負担してくれているが、破産者に余裕がでたときに、2万円を支払ったことがあるという意味とのことでした。
本事例の結末
本申立書の内容が不十分でしたので、管財人から詳細に聞き取り、追加調査をしましたので、本破産者の破産に至る事情がよくわかりました。
これをまとめて、裁判所に報告するとともに、不十分であった申立書類一式を再作成し、これも裁判所に提出しました。
事情聴取の中で、破産者には、免責不許可事由がないことも判明しました。
本事例に学ぶこと
本件破産事件が裁判所から配転される際に、担当の書記官から、申立内容が不備であり、なかなか補正されないために、管財事件となった旨の説明を受けました。つまり、管財人の手で、申立ての事情やその他を調査報告してもらう事案と説明を受けました。
珍しい指示でしたので、申立代理人の立場で、本事件を再調査する意味と捉え、さらに、債権者にも十分な情報の配当が可能なように、聞き取り、調査をしました。
本破産者は、体調がすぐれないことが多く、管財人面接も何度も設定し直しましたが、管財人の調査にも真摯に対応してくれましたので、なんとか、第1回集会期日に間に合わせ、異時廃止として終了させることができました。
当事務所でも自己破産事件の申立てについては多数の経験がありますが、裁判所からその申立内容が不十分とされた場合には、その追完指示にも適時適切に対応しております。
よって、それが不十分であるから管財事件とするという経験はありませんでした。
この管財事件は、自戒も込めて、依頼者には誠実に、裁判所には適切な申立を行うことの重要性を再認識しました。
弁護士 榎本 誉