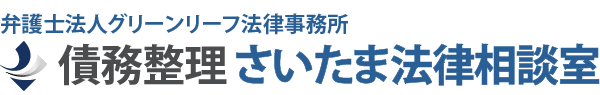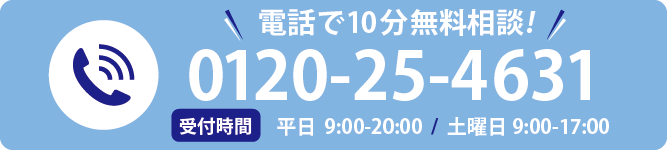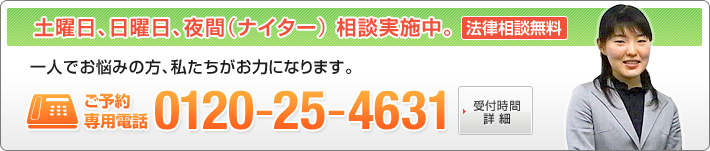紛争の内容
破産者となった法人の代表者は、25歳ころから、携帯電話販売会社への派遣の仕事をしていました。令和2年に、個人事業として、携帯電話販売会社への従業員派遣の自営業を立ち上げました。令和3年に、個人の自営業を法人成りさせ、株式会社を設立しました。同社の本店は、代表者の自宅マンションにおき、同所を事業所としました。同社は、携帯電話販売会社への従業員派遣に特化した会社です。
代表者の個人事業を法人なりさせた後、月の売り上げは300万円から500万円位とのことであり、多い時には、派遣従業員を10名抱えていました。派遣元からの報酬以外の諸々の経費を引くと、5%くらいが同社の利益(粗利)となるくらいだったとのことです。これでは、代表者個人に対する役員報酬(月額)を賄うことができず、当初は分割して支払う形にしていたとのことです。
令和3年、売掛金の未回収の問題が発生しました。これは、同社の派遣先である、携帯電話販売会社に対して、売掛金200万円弱を有していました。
取引先の同社は、携帯電話会社の販売会社の一次下請けであり、破産法人は、二次下請けです。
一次下請けの派遣先会社から、従業員引き抜きがあるとして、損害賠償請求だとされ、結局、2~3か月間の紛争となりました。先方からは、破産会社の売掛金に対し,損害賠償請求権で相殺するとして、一方的に支払ってもらえなかったとのことです。
しかし、破産会社は、その申入れには承服できないと争ったそうですが、先方に代理人弁護士が出て、破産会社への支払には応じてもらえませんでした。そして、先方には代理人弁護士から、破産会社への同売掛をあきらめる内容の合意書を交わす提示を受けましたが、破産会社は合意書を取り交わさなかったとのことです。
結局、この破産会社にとっては、大きな売掛金である200万円の入金もありませんでした。そもそも、資金繰りに余裕のある会社ではなかったため、他社からの売り上げから回すだけでは到底足りませんでした。
この経済的窮状において、破産会社はさらに借り入れをし、また、代表者個人としても借り入れをして、従業員給与の支払や返済などに回したそうです。
この破産会社においては、携帯電話販売会社への人材派遣要請の仕事は順調にあったそうです。しかし、借入などへ返済が厳しい状態は、令和3年からこの会社を廃業することを決意するまでの令和6年9月まで続いたとのことです。破産会社においては、派遣要請の仕事はあったのですが、薄利であるために、キャッシュフローの改善は見込めず、このままでは経営は無理だと判断し、会社の廃業を決意したとのことでした。
代表者は、会社の窮状を感じているからか、全従業員との雇用関係を令和6年9月末日付で終了し、社会保険関係、雇用保険関係なども社労士さんにお願いし、完了させ、その後、同社の破産申立依頼をしたものです。
代表者には、住宅ローンの抵当権をついた自宅マンションがありました。経営していた会社の破産申立準備を行いながら、再就職は飲食店アルバイトをしていましたので、住宅ローン付き個人再生手続は選択しませんでした。住宅は、競売手続に付されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
従業員関係の解消もつつがなく済んだ後の正式依頼でしたので、特に支障なく申立準備を行いました。
破産管財人には、売掛先とのトラブルについては、改めて、詳細に報告し、同社への債権回収は、破産管財人に委ねました。破産管財人は、同社への債権回収の対応の手段をとったようですが、結局、裁判所の許可を得て、同売掛金としては、早期の回収不能、回収見込み債権も高額ではないとして、破産財団から放棄しました。
法人の破産手続は、配当に充てる財産も形成されなかったとして、代表者個人の破産手続の終了前に終結されました。
他方、代表者個人の破産手続において、破産管財人は、競売手続中の自宅マンションの任意売却を行っていました。
管財人は、購入方をいろいろあたったようです。
しかし、結局、競売手続の申立権者の、売却承認の基準価格が、残ローンの9割と高額であり、その金額での購入者希望者が現れなかったとのことです。
そこで、法人破産の終了した、次の回となった、代表者個人の債権者集会において、同マンションを破産財団からの放棄許可を申請し、許可を受け、代表者個人の破産手続も終結となりました。マンションは競売手続によって処理されることになります(別除権)。
なお、代表者は、会社の運転資金を代わりに用立ててくれた方の、月額返済金を立替払していたことが、破産申立前に判明しました。その方は、法人の運転資金を代表者が用立てた資金のもととなったとのことで、代表者の破産債権者の一人でした。これは、管財人により否認権対象行為とされ、代表者が立替払した金員の取戻しがなされます。代表者には、今後の送金を禁じ、その受け取り分の返還を受け、当事務所が預かり、破産管財人に、引き継ぎました。よって、破産管財人は、その報告と当事務所の対応を相当と認め、否認権行使をする必要がないと判断しました。
本事例の結末
法人も、代表者個人の破産手続も、いずれも異時廃止となりました。
また、代表者には、過去の多額の金銭を費消した公営ギャンブルの経験がありましたが、それを踏まえても、裁判所の裁量により、免責が許可されました。
最後の債権者集会、免責審尋期日後に、破産会社代表者から、「会社役員にいつ頃になればなれるか。」と相談を受けました。なんでも、昔の同僚が経営する会社の経営陣に入ってほしいという要請がだいぶ前からあり、破産者は、飲食店アルバイトを辞めて、収入が不安定でしたが、破産手続きが終わってから就任したいと回答していたとのことでした。
この質問に対し、旧来の商法では、破産者は取締役になれないという欠格事由に該当しましたが、現在では、その規定は削除されているので、取締役を選任する株主が認めれば、破産手続中の破産者も、会社役員である取締役になることは、法律上は可能であると回答しました。
ただ、破産手続をとったことで、信用情報に登録されておりますので、取締役に就任した会社が銀行などから融資を受ける際に、役員の信用情報上の問題から、融資を受けられなくなることもないではないと説明しました。
本事例に学ぶこと
法人の破産申立依頼に際し、弁護士としては、債権者対応はもちろんですが、まずは、従業員との雇用関係の終了を避けて通れません。
しかし、本件ご依頼では、既に、雇用関係終了時期も予定され、従業員たちも十分承知しているとのことでした。また、事前に、社会保険関係の処理も、社労士のアドバイスを受けながら、済ませておりましたので、ご依頼後は、従業員関係の問題への対応はほとんどとありませんでした。
また、本法人は、代表者の個人事業からの法人なりをして、それほど時間が経過していない、よって、事業規模の拡大もそれほどでなかったために、会計資料、決算資料なども散逸していませんでした。
また、自宅マンションが本店所在地であり、事業所本部でもありましたので、事業所の閉鎖、明渡の問題もありませんでした。
代表者は、当事務所に本破産申立依頼をする頃から、他社の会社役員への就任を求められていたようですが、代表者は、法人をきちんとたたみ、個人の破産手続も終了させてからでないと、誘われている会社に迷惑をかけかねないとして、慎重に対応されたのでした。
賢明な判断だったと思います。
本代表者のように、次の仕事の就任見込みが立っている方もあります。
会社の経営者の、最後の経営責任は会社をきちんとたたむこと、債務超過であれば、破産手続を終結されることとなります。
当事務所は、そのお手伝いができますので、ぜひともご相談、ご依頼ください。
弁護士 榎本 誉